�P�D�͂��߂�
2003�N3��28�|31���ɓ��k��w����L�����p�X�ŊJ�Â��ꂽ���{�����w���58��N�����ɂ����āC3��28���ߌ�C���p�����w����i�_�ސ��w�j�Ɠ��{�����w����i��䍑�ۃZ���^�[�j�Ƃ��s�u��c�V�X�e���Ō��сC��L���œ��{�����w������番�ȁE���p�����w��p�������番�ȉ�E���{��������w��̋������V���|�W�E�����J�Â��ꂽ�D���{�����w����̍����́C�O���F����`���i�����_�H��H�j�C�㔼�F�쏟�����i����勳��j�C���p�����w����̍����́C�O���F��؍P�����i���C�嗝�j�C�㔼�F�����Ύ����i������H�j���Ƃ߂��D
�v���O�����̓��e�i���͉��p�����w����j
(1) ���̂˂炢
�ђ˔��j�i�����H�ȑ�j���C�c�����F�i�����������\���Z�j�C�쑽���i�c�䍂�Z�j
(2) ���{�����w��̋���ւ̎�g��
�k���a�v�i���{�����w���EICU�j
(3) ���p�����w��̋���ւ̎�g��
�㓡�r�v�i���p�����w���E����H�j��
(4) ���{��������w��̋���ւ̎�g��
���c����i���{��������w���j
(5) ����_��i�Q���҂���̎��^�������܂ށj
�i�@�x�@�e�@�j
(6) ��Ƃ���̏����̌����ҁE�Z�p�җ{������ւ̊��ҁ\�j���[�g���m���o�Z���T�J���Ɏ�g��Ł\�@
�@�@ ��n�P�v�i�l���z�g�j�N�X�j��
(7) �V�w�K�w���v�̕����ō��Z���͉����w��ł��邩
�����r�v�i����@�����j
(8) �������_
�Q�D�u���̊T�v�Ɠ��_�̓��e
�i�ȉ��CJPS�F���{�����w��CJSAP�F���p�����w��CPESJ�F���{��������w��
��\���j
(1) ���̂˂炢
3�w������V���|�W�E���J�Â̌o�܂ƁC�p�����邱�Ƃ̏d�v���Ȃ�тɕK�v�����q�ׂ�ꂽ�D
(2) ���{�����w��̋���ւ̎�g��
�܂��C��������̈Ӌ`�Ƃ��āC�@�Ȋw�Z�p�����̂��߂̊�b�w��C�A�����F�����w�̒m���ɂ�鐢�E�ρE�����ρE�F���ρC�B�����w�̕��@�_�i���͓I�E�����I�E���ʊW�E���f�����E��ʉ��Ȃǁj�̑�����ւ̔g�y���ʂ�������ꂽ�D���m�u�ǂ�����Η��Ȃ��~����̂��v�����p����C�@�p�������w���Â� Paperclip Physics�C�A���Ǝ��ƂƂ��čs����Science Week�C�B�`�����痝�Ȃ̎��Ǝ��Ԑ��̓��p��r���Љ�ꂽ�D�����w�̕��@�_�ɂ��Ă̋c�_�����ɁCEUPEN�ōs���Ă���C�u��������ɂ��镨���w�̃~�b�V�����v�̒��Ɂu�����w�̋���́C�����Ӗ��ł̕����w�ɗ��܂炸�C���̕��͓I�v�l�͍L���m�I�����Ɋ�^������̂ł��飂Ƃ��邱�Ƃ��Љ�ꂽ�D�܂��CFeynman�̌��t�hNature
does not read textbooks of physics, chemistry, biology etc. separately.�h�ƂƂ��ɁC�����w�I�Ȏv�l�����w��p��ȂǂƓ��l�ɍ����̑f�{�ł���ׂ����Ƃ����l�����������ꂽ�DJPS��������ψ���̂���܂ł̊����Ƃ��āC����������E��������ɂ����镨���w����̌����C�����w�̕������磎��̊��s�C�����Z�������Z�~�i�[�C�����J�w���C���Ȋw���琭��Ɋւ��錟���C��JABEE�C�����E��A�g�C���Љ�ꂽ�D
�w�K�w���v�̂̒��́u��b�Ȗځv�ɂ��āC�ȉ��̃R�����g���������F�u���Ȋ�b�v�c���R�ρC�����E�l����(question-oriented)�C�u���ȑ����`�v�c�����ƃG�l���M�[(�����E���w)�𑍍��I�Ɍ��錩���E�T���\��(skill-oriented)�C����ȑ����a��c���l�Ȑ����Ǝ��R(�����E�n�w)�𑍍��I�Ɍ��錩���E�T���\��(skill-oriented)�C�����̈ʒu�t�����B���D���̞B��������w�����Z���^�[�����i�ȉ��C�Z���^�[�����Ɨ����j�̑I���̎d���Ɍ���Ă���D�������̎��{�\��ł́u�����T�v�Ə�L�u��b�Ȗځv�Ƃ��������Ԙg�ɒu����C���̂�������1�I���ɂȂ��Ă��邪�C����́u��b�Ȗځv�̈���K�C�ł���Ƃ����l�����Ɩ�������D����ɑ���JPS��e��w����ӌ������o���ꂽ�D�܂��C�u���w��b�v�́u���Ȋ�b�v�Ɠ����l�����łł��Ă��邪�C���{���w��́g����w��b����Z���^�[�����ʼnۂ���ɂ͎��������ł���h�Ƃ����ӌ����o���Ă���C����͗��ɂ��Ȃ����l�����ł���D
�@���ɁC�u����ɂ�����peer review�v�ɂ��ĕ��s��ꂽ�F����w�]���̂��߂Ɋ��Ɂu��w�]���E �w�ʎ��^�@�\�v�C�u��w�����v������D�����{�����w����@�@JABEE�𐄐i���Ă��邪�C����͉Ȋw�ҁE
�Z�p�҂ɂ�鋳���peer review�ɂ�����C�R�����鑤���R�������鑤�����ɋ�����P�ɂȂ���D�Ȋw������̐R���͂��̐���ɂ���D�����B�ł͊��ɍ������z���������w�Ȃ�peer
review���s���Ă���CSocrates�v��ƘA�����Ă���D
�@2003�N3��25�|27���ɕ��ȏȎ�Âōs��ꂽSSH(�X�[�p�[�E�T�C�G���X�E�n�C�X�N�[��)�̌𗬉�̕��������F�S����SSH26�Z���琶�k4���Ƌ��t2�����Q�����č��h�D4�e�[�}�ɂ��Ċe26����4�g�ɕ�����ăO���[�v�������C��������������Ńv���[���e�[�V�����D��ҁE�����̌𗬂��d�v�ł���Ǝ��������D
����C�������́C���Ȋw�j���[�X�ɊS�����悤�ɂ��C�V�����m����excitement
������̏�Ɏ����ނׂ����C�������w���C�����C���w�C�H�w�̉��ɉB��Č����ɂ����Ȃ��Ă��������C������������ۂɓ`���I�ȕ����n�����łȂ��C�z�b�g�ȉȊw�Z�p��g�߂Ȍ��ۂ��g���ĕ�����������K�v������C��20���I�̕�����O��Ƃ�������̉\��������̂ł͂Ȃ����C�Ƃ��������������D�܂��D�w��̉ۑ�Ƃ��āC��2005�N���ە����N�ւ̎�g�݁C�������O�����v���C�����I�����s�b�N�ւ̎�g�����C��More
women in Physics(girls in Physics)�C��������ꂽ�D
(3) ���p�����w��̋���ւ̎�g��
�܂��CJSAP�̋���ւ̎�g�݂Ɋւ����{�I�ȍl�������q�ׂ�ꂽ�F20���I�㔼�C���{�̉Ȋw�Z�p�C�Y�ƁC�o�ς͑傫�Ȕ��W�𐋂��Ă������C�ߔN�͎Y�Ƃ̋���Z�p�̍��ۋ����͒ቺ���i�݁C���S�̂Ƃ��đ傫�ȓ]�@���}���Ă���D���̏����������̔��W��ڎw�����߂ɁC���݁C�V�����Ȋw�Z�p�̑n���ƐV�Y�Ƃ̑n�o�C����Ɋւ��l�ނ̈琬�������]�܂�Ă���D���������̈���ŁC���{�̎�҂̗��ȗ��ꂪ�����悤�ɂȂ��ċv�����D���̂悤�ȏ̒��C��N�w�ɑ��闝�ȋ���E�Ȋw�Z�p����̏d�v���͏]�������傫���Ȃ��Ă���C��Ƃ�w�������ɍv�����邱�Ƃ����߂��Ă���D���̂悤�Ȕw�i�܂��CJSAP�ł́C��N�w�̗��ȗ����Z�p�����͂̒ቺ���ɂ߂ďd�v�ȉۑ�ƔF�����C�����ʂ����łȂ��C���Ȃ�Z�p�Ɋւ��鋳��ʁE�l�ވ琬�ʂł��v�����ׂ��ł���Ƃ̕��j�����肵���D�܂��C�{���ψ���C�x���C���ȉ�̊w����g�D�̘A�g���͂̂��ƂɁC���ȋ��瓙�Ɋւ���L����̂����g�݁C���w��C���g�D�Ƃ̘A�g���͂ɂ�闝�ȋ��瓙�Ɋւ����g�݂����i���Ă���C��������@�ւɂ�鋳��֘A���Ƃւ̋��͂₻����ʂ������{�̋Z�p����юY�Ƃ̔��W�ɍv�����邱�Ƃ��d�����Ă���D
���ɁC����Ɋւ���JSAP�Ǝ��̎�g�݂��Љ�ꂽ�F����Ȋw�Ɛ����̃t�F�X�e�B�o����c����Ɋւ���JSAP�S�̂Ƃ��Ă̏��߂Ă̎�g�݂ŁC�x���Ɖ��p�������番�ȉ�̋��͂̂��ƂɊ��E���{�D��N�w�̗��ȗ���ւ̑Ή��Ƃ������ƂŁC���E���w���i�ꕔ���Z�����܂ށj�ΏہD��1���1995�N�ɋ���ŊJ�ÁC���̌㖈�N�C�H�G�w�p�u����̊J�Òn��ŊJ�Â��Ă���D��7��i2001�N�j�͖��É��ŊJ�Â���C18,000�l���Q���D������t���b�V�����ȋ�����c1997�N����C�x���̋��͂Ŋ��E���{�D���E���w�Z�̋�����ΏۂƂ��C�ŐV�̉Ȋw�Z�p��m��@���D���N10����x�J�ÁD�������V���|�W�E����cJSAP����ΏہD�n�����L���Ȑl�ނ̈琬�Ƃ��̕���ɂ��čl����V���|�W�E���ŁC1998�N����u�N���ɊJ�ÁD������J�u���cJSAP�̐�[����̓��e����ʂ̕��X�ɗ������Ă��炤���߂̌[���I�ȍu����ŁC�u�N���ɂ��낢��Ȓn��ŊJ�ÁD����X�N�[���`��c�t�G����яH�G�w�p�u��������ɁCJSAP�������ȑΏۂƂ��āCJSAP�S�̂Ɋւ��e�[�}��I�сC�u���Ɠ��_��ʂ��ė����ƍl�@��[�߂�D
�@JSAP�͑��g�D�Ƃ̘A�g�ɂ�鋳��ւ̎�g�݂��d�v�ƍl���Ă���C�Ƃ�����ŁC���̎�g�݂��Љ�ꂽ�F��JABEE�cJSAP��2001�N���犲���w����Ƃ���JABEE�ɎQ���DJPS���͂��߂Ƃ��镨���n�w����ƘA��������A�g���Ċ�����W�J�D�R���̈�Ƃ��Ģ�����E���p�����w�֘A���죂�V�݁D���݂܂łɁC����w�̕����n�C���p�����n�w�Ȃ̐R�������{�D��CPD(�Z�p�Ҍp������)�c��Ƃ̋Z�p�ҋ���ɑ��鍡��̎�g�݂ŏd�v�D�Ō�ɁC����̕����Ƃ��āC�ȉ��̎�������グ��ꂽ�F��JSAP�Ǝ��̎�g�݂̏[���E���W�D�����g�D�Ƃ̘A�g�ɂ��JABEE�CCPD���̎�g�݂̏[���E���W�D�������I�����s�b�N�Ȃǂ̐V������g�݂Ɋւ��錟�����O�����ɍs���D
�@�u����C�k�������u�Z�p�җϗ��E�H�w�ϗ��ɂ��Ă̎�g�݂́C�����Ȃǂ̕��L�������܂�ł���̂��v�Ƃ������₪����C����ɑ��āC�u�ߋ�2�N�قNJw��Ƃ��Č����𑱂��Ă��āC��N�w�ϗ��j�́x�𐧒肵���D�Y�ƂƊ֘A�������܂ŕ��L���l���Ă��邪�C����C����̓I�Ȏ��Ⴊ�o�Ă��邱�Ƃ��\�z����C����ɑ��ėϗ��ψ����ݒu���ČX�ɑΉ��������ƍl���Ă���D����̃X�N�[���`�́C���̂�����̌������n�߂悤�Ƃ��āw�H�w�ϗ��E�Z�p�җϗ����l����x�Ƃ����e�[�}�Ŋ�悵���v�Ƃ̉��������D
(4) ���{��������w��̋���ւ̎�g��
�܂��C���ꂩ��b�����e�͉�l�̍l���ƒf��ꂽ��ōu�����n�߂�ꂽ�F
�@�Ȋw�Z�p����̖ڕW�́C�@�Z�\�E�Z�p�̋���c���Ƃ̂��߂̃v���t�F�b�V���i���ȋZ�\�E�Z�p�C�A�Ȋw�I�f�{�̋���c���ׂĂ̐l(�s���C�_���C�����C���l�C�����ƁC�c���Ȃǂ̔����)�̂��߂̉Ȋw�C�B�n����(�Ƒn�C�n���C�n�o)�̋���c�A�J�f�~�b�N�ȉȊw�Z�p�D����ɑn�����ɂ́C�@�l�̑n�����i�V�ˁC�����ƁC�Ƒn�j�C�A�W�c�̑n�����i�`�[�����[�N�C�����������C�����O���[�v�j�C�B�g�D�̑n�����i�w�h�C�����̐��C�v���W�F�N�g�j��3������D19���I�͢�l�̑n������C20���I�͢�W�c�̑n������ɏd�_�����������C21���I�͢�g�D�̑n��������d�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����D�Ȋw�Z�p�����ł̑n�����ɂ́C�͕�I�łȂ��C�ތ^�I�łȂ��C�V�K���C���I�C�G��I�C�J��I�ł��邾���łȂ��C��`�I�\�͂����h��(����Ȃ�)�Ŕ������邱�Ƃ�C�|�p�╶�w�̕��������Ɗ֘A���邱��(����E�n��E�����E����)�C�Љ�̑n���╶���̑n���Ɍq���邱�Ɠ����K�v�ł���D�n������|��������s����ŕK�v�Ȃ��Ƃ́C�@�n������j�Q������q������(���E�l�ߍ��݂��~�߁C����I�E�����I�w�K�����シ��)�C�A�D��S�E�T���S�̈琬(��蔭���́E�������͂�����C�_��Ȏv�l�E�ᔻ�I�l�@�̌P��)�C�B�}�j���A���I�łȂ��C�n���I�ȋ���(���t���g���D��S�������C�����Ƒn�I�ɍs���\�ǂꂾ���D��S�����߁C���@�t���ł�����)�C�C�n�����̋����Ƒ��i(�����R���N�[���C���{�R���C�����I�����s�b�N�C�Ȋw�̍ՓT�Ȃ�)��4�D
����܂őn�����̋���ɂ��Ă̌����͂��܂�s���Ă��Ȃ��D�}�X�R�~��l�̈ӌ��E�咣�ł͂Ȃ��C�܂����ጤ����A���P�[�g�����łȂ��C�̌n�I�Ȋw�I�������s�����Ƃ��K�v�D����]�܂��n�����̌����ۑ�́C�Ⴆ�C�C���X�s���[�V�����Ƃ́H���@�͂͋������邩�H���R�̃`�����X�����\�͂́H�n�������s���y���ނɂ́H�n�����̕]���@�́H�V���̍˔\�����o�����@�́H�{����k���t����\�͂́H�ȂǁD�n�����͉Ȋw�Z�p�҂����ɕK�v�Ȃ��̂ł͂Ȃ��C���R�Ȋw�I�ȑn������|�����߂ɂ͌|�p�I�Ȋ������𗧂D
(5) ����_��
�܂��C�e�u���҂ɒZ���R�����g������ŁC���Ƃ̓��_�ɓ������F
�k����F�u�n�����v�Ƃ����Ƌ���̏�ʂł��u�l�̑n�����v���������ꂪ�������C���c�搶�̍u���ɂ������u�W�c�̑n�����v��u�g�D�̑n�����v���傫�ȗv�f�ł���D���SSH�̍��h�ŁC�Ȋw�Z�p����ɂ����ăR�~���j�P�[�V�����\�͂��d�v�ȗv�f�ł���Ǝv�����D
�㓡��FJSAP�͉���̔����ȏオ��Ƃ̋Z�p�҂Ƃ������Ƃ�����C��҂̗��ȗ���͏d�v�Ȗ�肾�ƔF�����C�Z�p�҂̐��U����C��w�ɂ�����H�w����ɁC��肢�������͂𒍂��K�v������ƍl���Ă���D����CJPS��PESJ���������Z�̗��ȋ���̏[���ɂ���܂ňȏ�ɗ͂𒍂��ł��������̂ƘA�g����JSAP�����͂��Ă��������D
���c��FPESJ�́C��w�̍H�w�n����Ƃ��������������Z(��Ƃ��Ē����Z)�̗��ȋ���ɏd�_��u���Č������Ă��Ă���D����́C���������Z�̋����ŁC��w�E�Z��̋�����3�����x�C���̑���2�����x�Ƃ����\���D�Ȋw�Z�p�I�f�{�̏[�����d�v�ł���C�u�n�����̋���v�͂���܂ł��܂茤������Ă��Ȃ��������C���ꂩ�瑊�ΓI�ɏd�v�ɂȂ��Ă���D����܂ł͌l�̑n�����C�V�˂ɂ���đ傫�Ȑi��������������ꂽ���Ƃ������������C���ꂩ��̉Ȋw�Z�p�́C�W�c���邢�͑g�D�őn��������������Ă��邱�Ƃ������Ȃ�D����𐄐i���邱�Ƃ��C���ꂩ��̉Ȋw�Z�p����̑傫�ȉۑ�ɂȂ�D
�㓡��FJSAP�ł͉���ɋZ�p�҂������̂ŁC�Z�p�җϗ��E�H�w�ϗ��̖��͊w��Ƃ��čl���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƔF�����Ă���D��w�̗��w�����̑��Ǝ҂���Ƃɓ����Ă���D��Ƃ̋Z�p�҂�JPS�ɏ������Ă���DJPS�Ƃ��Ă��C�Z�p�җϗ����l����K�v������Ǝv�����CJPS�ł͋Z�p�җϗ��ɂ��č��܂łǂ̂悤�ɍl���C�c�_���Ȃ���Ă����������Љ�����������D
�k����FJPS�ł́C�ϗ��ɂ��Ċw��Ƃ��ċc�_���Ă��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����DJPS����̑����͌�������@�ւɂ��āC�����ōs���Ă���Ȋw�I�����ɑ���ӔC�����o���邱�Ƃ��C����o���ꂽ�w���̉Ȋw�I�����ɑ���ӔC�E���o�ɂȂ���Ǝv���D���̈Ӗ��ł�JPS�͂��̖��ɊS�������Ă����ׂ����Ǝv���DJSAP�̋Z�p�җϗ��ւ̎�g�݂����ЎQ�l�ɂ������D
�㓡��FJSAP�́C��w���̌����@�ւɂ�����̔����߂��������D�ϗ��̖��͂��ׂẲ���ɊW������D���̓_�ł́CJPS�Ƌ��ʂ��镔���͑����DJSAP�Ƃ��Ă�����CJPS�ƘA�g���ėϗ��̖����ꏏ�ɍl���čs�������ƍl���Ă���̂ŁC��낵�����肢�������D
�������F3�w��ŋ��͂��ĉp���̕�������_��������邱�Ƃ��ǂ̂悤�ɍl���Ă����邩�D�܂��C���ە����I�����s�b�N��A�W�A�����I�����s�b�N�ɑ���3�w��̉�͂��ꂼ��ǂ̂悤�ɂ��l�����D
�㓡��F��������Ɋւ��鍑�ێ�������Ă������Ƃ�JSAP�Ƃ��Ă͋c�_���n�߂Ă��Ȃ����C�l�Ƃ��ẮC���炪�ǂ̊w��ɂƂ��Ă����ɑ傫�Ȗ��ɂȂ��Ă��Ă�����l����Ƌ���Ɋւ��錤�������\���Ă����ꏊ����邱�Ƃ͏d�v�Ȃ��Ƃł���CJSAP�Ƃ��Ă���������K�v�����邩������Ȃ��D����͈�̊w��ōs���̂ɂ͖���������Ǝv���C�������̊w��A�g���ċ���Ɋւ����厏���o���Ă������Ƃ��������ׂ����낤�D�܂��C�����I�����s�b�N�ɑ��Ăǂ̂悤�Ɏ��g�ނ��Ƃ������ɂ��ẮC�O�����Ɍ������Ă���Ƃ���ł���D�����C����Ă݂Ă��܂������Ȃ������Ƃ������Ƃł̓}�C�i�X�̌��ʂ��c���\��������̂ŁC����Ԃ������邩������Ȃ����C�\���Ȍ������s���C������������ōs�������ƍl���Ă���D
���c��FPESJ�ł�1986�N��IUPAP�̕�������̍��ۉ�c����q��w�ŊJ�ÁD���̌�C�j���[�Y���^�[�̌`��ICEC�Ƃ������̂̉p���̋I�v���o���Ă���D���p��͉p��D���\���e�͑����Ȃ����C���ɏo�����_���̗v���PESJ�̒���activity�Ȃǂ̍��ۓI�ȘA���ɗ��p�D�l�I�ȓ��e�ł́CAmerican
Journal of Physics������ł��\�D�ȑO�́C�����local�Ȃ��̂ł��荑�ɂ���Ă��Ⴂ���������D�������C�O���[�o�����C���ۉ��̒��ŁC���ꂩ��͂��̂悤�ȏꂪ�K�v�D���ꂩ��͕K�������_�����̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��āC�C���^�[�l�b�g��Ō��J����ق�����������̂ł͂Ȃ����D
�k����F���{�ł��l�X�Ȋ������s���Ă���C������ǂ�����Α����̐l�ɍL�߂邱�Ƃ��ł��邩�͑厖�Ȗ��D���ۓI�ɂ�����share����ɂ͂ǂ������炢�����D2002�N10���Ɋ؍������w��ɍs�����D��������̃Z�b�V����������C�l���Ă�����͑S������������(���ȗ���C��w�@�l���Ȃ�)�D������抪�������O���[�o�������Ă���C�p�������o�����݂��ɒm�b���o���₷���Ƃ������Ƃ͂��邾�낤�D���̂��Ƃ́C����C�����n�w��ōl����ׂ����Ƃł���D���ݓI�ɂǂ̂悤�Ȋ����┭�\�ɒl������̂����邩�����邱�Ƃ��K�v�D���{�����M���邱�Ƃ��厖�ł���C�O�����ɍl���Ȃ��Ă͂����Ȃ��ۑ肾�D�܂��C�����I�����s�b�N�ɂ��āCJPS�ł͂��炽�߂Ă���2�N�قnj������Ă��Ă���C����JSAP�CPESJ�Ƃ̊ԂŌ����������n�߂Ă���D���E�ɑ���O�ɓ��{�̒��ł��̂悤�ȍ��Z���̏W�܂肪�ł��邩�ǂ������������C����C3�w����͂��Đi�߂Ă������ƂɂȂ邾�낤�D
�������F10�N�قǑO�ɁC�O����́i�������͓��{��ł��j��������̌����_�����̔��\�̏ꂪ�~�����Ƃ�������������C�������[�L���O�O���[�v�������Ċw��Ŏ��v���E�����������ʁC�܂�needs������Ȃ����낤�Ƃ������_�������D���낢��Ƃ߂Ă��������ʁCneeds������K�v�ȏ������`�̌��݂́u��w�̕�������v���ɗ����������D���炽�߂�Journal�����邱�Ƃ���������ۂɂ��Cneeds�̒�������n�߂邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����DICEC�j���[�Y���^�[�́C���N�����������Ȃ���Web�ɂ����ڂ���`�ɂ����D
�쏟���F3�w��̘A�g�̕����Ɋւ��āC�e�n���ɂ�����n��̏������Z�̐搶��3�w��Ƃ̘A�g�Ȃ�тɂ����ɑ���3�w���̎x���̂�����C����ɂ�����u�����v�̕K�v���𑼒c�́E���w��ɔF�����Ă��炤���߂ɕK�v�Ȏ�g�݁C����2�_��3��Ɏf�������D
�k����F���ۓI�ȘA�g�Ɠ����ɁC�g�߂ȂƂ���ł͏������Z�̐搶���Ǝ������Ƃ̘A�g���d�v�DJPS�ł́C�x�����Ƃɍu������s���Ă��邪�C�����Ɠ���I�ɒm�b���o���������ق��������D������x�̓{�����e�B�A�x�[�X�ōs�킴��Ȃ����C������w��Ƃ��Ăǂ̂悤�Ɏx�����Ă����邩�͍���̉ۑ�D�����Ƒ��w��Ƃ̊W�ɂ��ẮC���낢��Ȉӌ�������Ǝv�����C�u�d�C�v�C�u���w�v�C�u�����v�C�u���w�����v�Ȃǂ��ނɂ��Ȃ���u�����v�����悤�ȋ���i���邢�͋���ے��j��{���ł��āC�����w�Ҏ��g���u�����v��ʂ��đ��̐��E�����邱�ƂŁC�l�X�ȕ���̐l�ƃR�~���j�P�[�V�����ł���Ƃ����Ǝv���D
���c��F�n���Ƃ̘A�g�ɂ��ĕt��������ƁC�u�Ȋw�̍ՓT�v�Ɋ֘A���������̒��ŁC�����w�Z�̐搶���Ƃ̘A�g��C���Z���E���w���̎Q���Ŏ��т��グ�Ă��Ă���DJSAP�́u���t���b�V�����ȋ���v�ł����������C�u�Ȋw�̌��Ղ�v�i���j�ł��������炢�͏��w�Z�̐搶�����ϋɓI�Ƀf�����X�g���[�V���������s���Ă����悤���D���̂悤�Ȓn���ł�activity��ʂ��đ��݂̏�������h���ɂ��Ȃ�C�Ȋw�ɑ��鋻����S�����߂铭��������D���ケ�̂悤�ȃO���[�v����������ɂȂ��Ă�������̂ł͂Ȃ����D
�㓡��FJSAP�ł͒n��Ƃ̘A�g�͂��Ȃ�s���Ă��Ă���D��Ȋw�Ɛ����̃t�F�X�e�B�o����C����t���b�V�����ȋ�����͎x���⋳��ψ���C�������Z�̐搶���̋��͂Ď��{���Ă��Ă���C���܂ł��Ȃ�̌��ʂ��オ���Ă���D����C�n��Ƃ̘A�g�͂����������W����������Ői�݂����D���c�̂Ƃ̘A�g�E���͂́C����ʂł́C�Ⴆ��JABEE�Ȃǂ�JSAP�����łł�����̂ł͂Ȃ��C����JPS�̋��͂Ă���C�����̊�����ʂ��Ċw��Ԃ̘A�g�͂���ɋ��܂��Ă������̂Ǝv����D����E�����ɊԐړI�ɊW������̂Ƃ��āC��j�������Q�棁C��ϗ���̖�肪����C�����ɂ��Ă͍���A�g������ɋ��߂Ď�g��ōs�������D����C��̊w��P�ƂŎ�g�߂邱�Ƃ͔��Ɍ����Ă���Ǝv����D�e�[�}���ƂɘA�g�̌`�͈Ⴄ��������Ȃ����C�������̊w����A�g���Ċ������邱�Ƃ͑�Ϗd�v�ɂȂ�Ǝv���D
���(�P)���F�X�̖���3�w��ŘA�g���Ă������b��3�w�����炠��C��ϗL�Ӌ`�ł������D���ꂩ���3�w��ŘA�g���ăV���|�W�E�����J�Â��Ă��������D
����F�����ƕ���������抪�����͂ƂĂ����l�ł��邪�C�����ɂ���3�w��ꂼ��̗��ꂩ�狤�ʂ̖��ӎ��������Ď�g��ł����邱�Ƃ��m�F�ł����D������肪����ɂ��āC����ɋ�̓I�ȋc�_���W�҂̊ԂŐi�߂��Ă������Ƃ����҂��Ă�܂Ȃ��D
(6) ��Ƃ���̏����̌����ҁE�Z�p�җ{������ւ̊��ҁ\�j���[�g���m���o�Z���T�J���Ɏ�g��Ł\�@
���Ď��̃m�[�x�������w��܂��x�����o���܂��C��ƁE�Y�Ƒ�����̎��_�ʼnȊw�Z�p����ւ̒��s��ꂽ�F�����ȗ��s���Ă��������J���̎p���ł́C���͂⍑�ۋ����ɏ��ĂȂ��D���������ɂ����ł��Ȃ����̂����Ƃɂ��Ď��Ƃ�i�߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��D����́C�ߋ��ɐl�ނ��|���Ă����p�m��^���邱�Ƃł��邪�C���{�̊w�Z�́C���{�ɂ����ł��Ȃ����Ƃ������Ă����̂��D�l�ނɂ͂܂��m��Ȃ����ƁC�ł��Ȃ����Ƃ������ɂ��邱�Ƃ������Ă������������D���Ď������̂Ƃ���ɗ���5�N�O�ɕč��Ŋ��Ƀj���[�g���m�̑��肪����Ă����D���Ď����]�����ꂽ�̂́C���E�ň�Ԑ��x�̍������d�q���{�ǂ��g���Đ��E�ň�Ԃ����f�[�^���Ƃ������炾�D����Ől�ނ̒m�����ǂꂭ�炢���邩�������邱�Ƃ��厖�����C���ꂾ���ł͏\���łȂ��D���E�̒N���m��Ȃ����Ƃ�������ɂ͉����厖�Ȃ̂��������ė~�����D���{�Y�Ƃ̎O�d�d�́C1)���{�����ł͌��ޗ����قƂ�ǎ��Ȃ��C2)�G�l���M�[�i�d�́j�������ł���C3)�y�n�����ɍ����ł���D�t��������Ɓu�l��������v���d�D���̂悤�ȃn���f�B��w�����āC�ǂ̂悤�ɐ��E�Ƌ������Ă����̂��D�h�����ċ����ł��Ă���̂͐ݔ������������p�ł��Ă��邩��D����Ȃɖׂ����Ă���킯�ł͂Ȃ��D�������肪�������ł���Ă��邩���������Ȃ��Ă͂Ȃ炸�C�ׂ���͂����Ȃ��D�����C���Ď�����KAMIOKANDE�ŗz�q����𑪒肵�����ƕ������D�r�b�O�o������10�b��ɂ��ׂĂ̗��q���ł��C���̗��q��200���N�����ĉF��������C�F���̗��j���L�����āC�����̑̂̒��ɂ���D���̗��q�͌��邱�Ƃ͂����Ă������邱�Ƃ͂Ȃ��D���̗z�q�̕���𑪂肽���Ƃ������Ƃ������D�ł��邩�ǂ����킩��Ȃ��������C���E���ŒN����������Ƃ��Ȃ����Ƃł��C�S�g�S��Ŏ�g�߂Ή��Ƃ��Ȃ���́D����ł͂��̂悤�ȍ����������ė~�����D
���^����
���F�������Ƒ́u�����v�ɂ��čl�����f�������D
��n���F���l�̂܂˂��Ă����Ă��邩�碒��ǂ����룂Ƃ������Ƃ��N����D�e�X�������̂���d�������Ă���������͎����Əo�Ă���D
���F���Đ搶�Ƃ̏o��͂ǂ������Ƃ���ŁH
��n���F�ŏ��C�h�C�c�̃f�C�W�[��3,000�{�̑��{�ǂ��g���Ď������s���\�Z���t�����Ƃ������ƂŁC����p�̌��d�q���{�ǂ���邱�ƂɂȂ����D��ςȖ������������t����ꂽ���C���ɕ������ʼn��Ƃ��������D���E�������ڂ���O�ŁC��ς��������f�[�^���o���D���̌�C���ǂ��̌��d�q���{�ǂ����E�̍��G�l���M�[�����w�̒��x�̍��������ɂ͂قƂ�ǎg����悤�ɂȂ�C���G�l���M�[�����̎����ł͍��ۓ��D���Ӗ��𐬂��Ȃ��Ȃ����D���Ď�����͍ŏ�25�C���`�̌��d�q���{�ǂ������ė~�����Ƃ���ꂽ��20�C���`���������D
���F�������ɓ����Ă���w���͌��C���Ȃ��D����Ă��邱�Ƃ�������Ď����̐g�ɂ��Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ��̂ł͂Ȃ����D�M�Ђ͐��E�I�ȉ�Ђ����C�V���Ј��ňꐶ�������Ȃ��Ј��͂��Ȃ����D
��n���F�����ȗ��C�m�����������ނ̂����炾�Ǝv���Ă��邩�炻���Ȃ�̂ł͂Ȃ����D�����肫���Ă��邱�Ƃ̒��ɂ�������Ȃ����Ƃ����邱�Ƃ������āC�h�����Ă��D���̉�Ђł����ɊW�̂��邱�ƂȂ玩������肽�����Ƃ���������ƌ������C�����̉肪�o�Ȃ��Ɨ\�Z�͏o���Ȃ��D�����Ŏd������������܂ł́C�l�̎d�������ďK���C�����Őg�ɂ���Ƙb���Ă���D�g�ɂ���Ƃ������Ƃ́C�w���m���Ƃ��ē��ɓ���邾���ł͂��߂��D20�C���`�̑��{�ǂ����Ƃ����C34�̐ӔC�҂���В������Ƃ������̂�����ł���Ɍ��܂��Ă���D�ł��邩�ǂ����͐S�z���Ȃ�������ƐV���L�҂ɘb�����炵���D��ł��Ȃ��ƌ��킸�ɂ���Ă݂룂ƌ����Ă���D���t���ړI��^���Ă����C�͏o�Ȃ��D�����Ō�����ƌ��������Ȃ��D
(7) �V�w�K�w���v�̕����ō��Z���͉����w��ł��邩�@�@�@�@�@�@�@
�܂��������ߎS�Ȍ����������ƌ��߁C����ɑΉ����邱�Ƃ��d�v�ł���C�u���Z���������w��ł��Ȃ����v�ƌ������ق����킩��₷�������m��Ȃ��C�ƑO�u���̏�C�{��ɓ���ꂽ�F
��w�l�E�����҂�������������̏ڍׂ܂Ő[���S�����K�v���́C���炪��w�������͊�Ƃōs������̌��ʌ���̂���(���ꂩ��͕]���̎���)�C������������̕����h�����߁C��2�_�ɂ���D�F���炪�����������炪�ǂ��Ȃ��Ă��邩������߂Â��ďڂ������Ă������ƂŁC���̖��_�������Ă���Ɗ��҂��Ă���.
|
�����N |
�{�s�N |
���w�Z |
���w�Z |
|
1958�N |
1961�N(��) 1962�N(��) |
628���� |
420���� |
|
1968�N |
1972�N |
628���� |
420���� |
|
1978�N |
1981�N |
558���� |
350���� |
|
1989�N |
1993�N |
420���� |
315�|350���� |
|
1998�N |
2002�N |
350���� |
290���� |
�@�@�@�@�\1�@�����w�Z�̗��Ȃ̊w�K����
2000�N6��26���ɑ�17�����{�w�p��c�����w�����A���ψ���Ţ��������E���ȋ���̌���ƒ�����\����(�ڂ����́C�����m��E����`�F���{�����w�
��55��(2000)�Cp.872). ���̒̓��e�́C1. ��w�l�E�����҂�������������ɂ��Ă̏\���ȗ������C2. ���ȏ�����̍S���̊ɘa���C3. ��w�����ɂ��e���͔����ɂ͍��Z�̎���\���Ȕz�����C4.
������������̓��e���\���ɔF��������ł̍���������C5. ��w�̋���̐��̐������C�ł���D���̒́C�O�������đi���鍀�ڂ�莩�������������đi���鍀�ڂ̕��������_���C�]���ƈ���Ă���D
���Ȃ̎��Ԃ��啝�Ɍ������i�\1�j�����́C��͓y�j�����x�݂ɂȂ������ƁC������́u�����I�Ȋw�K�̎��ԁv���قƂ�Ǘ��ȂƓ������炢�̎��Ԏg���Ă��邱�ƁD�u�m�������ł͂��߂��v�Ƃ����|�����̉��C������I�Ȋw�K�̎��ԣ�łǂ��������Ƃ��s���Ă��邩�C�������͒��Ӑ[�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ�.
�@�]���͒��w�Z�őS�����w��ł������C�V�w�K�w���v�̂ō��Z�����Ɉڂ��ꂽ���ځF�͂Ƃ˂̐L��/���ʂƏd���̈Ⴂ/�͂̍����ƕ���/�d���Ǝd����/���R�����^��(�Ζʂ̉^���͒��w�Z�ň���)/����/����/���̉��M�ƔM��/��M/�𗬂ƒ���/�d�͗�/�^����d�D���Z�i�w����9���ȏゾ��,���̂��������I���҂�3�����炢�D7�����炢�͏�L�̍��ڂ��C�ꐶ�C�w�Z�Ŋw�Ȃ��Ȃ�D
�@�]���͢����IB��Ŋw��ł������C�V�w�K�w���v�̂Ţ�����U��Ɉڂ��ꂽ����(�Z���^�[�����͈̔͂łȂ��Ȃ�)�F�^���ʂƗ͐ρC�^���ʂ̕ۑ�/�{�C���E�V�������̖@��/�c�g�Ɖ��g�C�g�̓`����/�X�y�N�g��/�d�E�E�d�ʁC�N�[�����̖@���C�d�C�͐��C�Ód�U���C�U�d���ɁC�Ód�Օ��C�L���q�z�b�t�̖@���C�R���f���T�[�C�Ód�G�l���M�[/�d�q�̓d�ׂƎ��ʁC���q�C���˔\�D������U����w�ׂ������w�Ԃ��Ƃ��ł��邪�C������U���I������͍̂����̂P���������Ȃ��D�܂��C�Z���^�[�����͢�����T��͈̔͂ōs���C������U��͉ۂ���Ȃ��D���������āC������U��Ɉڂ������ڂ́C���Ƃ��Z���^�[�����Ţ�����T���I���������Ƃ��Ă��C�K�������w��ł���Ƃ͌���Ȃ��D�Z���^�[�����Ţ�����T����Ƃ点�邩�ǂ����̋c�_������ۂ́C������T��̍��ڂɉ����܂܂�Ă��邩���\���m������ŋc�_���ׂ��ł���.�V�ے�����́C�Z���^�[�����Łg�����h��I�����������獂�Z�����̊�b���ł��Ă���Ƃ͑S�������Ȃ��Ȃ�D���̓_�C�v���ӂł���D�w���v�̂����炽�߂Č������K�v�����낤�D
|
���� |
�{�s |
�Ȗږ�(�P�ʐ�) |
|
1955 �N |
1958 �N |
[����(3)���w(3)����(3)�n�w(3)] �܂���[����(5)���w(5)����(5)�n�w(5)] ���2�Ȗڈȏ�I��K�C |
|
1960 �N |
1963 �N |
[����A(3)���wA(3)����A(4)�n�wA(2)] �܂���[����B(5)���wB(4)] ���4�ȖڕK�C |
|
1970 �N |
1973 �N |
[���Ȋ�b(6)�����T(3)���w�T(3)�����T(3)�n�w�T(3)]6�P�ʈȏ�I��K�C�{[�����U(3)���w�U(3)�����U(3)�n�w�U(3)]�I�� |
|
1978 �N |
1982 �N |
���ȇT(4)�K�C�{[���ȇU(2)����(4)���w(4)����(4)�n�w(4)]�I�� |
|
1988�N |
1994�N |
[��������(4)�@��IA(2)�܂���IB(4)���wIA(2)�܂���IB(4)����IA(2)�܂���IB(4)�n�wIA(2)�܂���IB(4)]2�敪2�Ȗڈȏ�I��K�C�{[�����U(2)
���w�U(2)�����U(2)�n�w�U(2))]�I�� |
|
1999 �N |
2003�N |
[���Ȋ�b(2)���ȑ���A(2)���ȑ���B(2)�����T(3)���w�T(3)�����T(3)�n�w�T(3)]2�ȖڑI��K�C(��b�܂��͑�����K���܂�)�{[�����U(3)���w�U(3)�����U(3)�n�w�U(3)]�I��(�Ȗړ����ڑI������) |
�@�@�@�@�\2�@�����w�Z�w�K�w���v�́@���Ȃ̕ϑJ
���̈���ŁC�]���́u�����U�v�Ŋw��ł������C�V�w�K�w���v�̂Łu�����T�v�Ɉڂ��ꂽ���ڂ�����(�Z���^�[�����͈̔͂ɂȂ�)�F���ꒆ�̓d���ɓ�����(�����̂�)/�d���U��(�����̂�)/��(�����l�͏���)/�g�����X/�d�g(����M�̎����̂�)�D�w�K�w���v�̢̂�����T��̓d�C�͈͈͂ȏ�̂݁D�d��(�d�E)���I�[���̖@�����Ȃ��i�������C�����̋��ȏ����w�K�w���v�̂ɂȂ��u�I�[���̖@���v���܂߂Ă���̂ŁC����͊w�Ԃ��ƂɂȂ邾�낤�j�D�܂��C�w�K�w���v�̉���́u�G�l���M�[�v�̍��ɁC�g�d�E���̓d�ׂ̈ړ��ƃG�l���M�[�̊W���������x�ɂƂǂ߂�h�Ƃ���̂ŁC���ȏ��ł͓d��i�d�E�j���g��u�h�����Ă���D
�@�]���́u����IB�v�Ŋw��ł������C�V�w�K�w���v�̂Łu�����T�v�ɂ��u�����U�v�ɂ��ڂ���Ȃ���������(�u�����U�v�܂ŗ��C���Ă��w�Ȃ�)�F�����I�Ȕg��\���������̎�/�����̂������ꍇ�̃h�b�v���[���ʁD���Z���ȏ��Ŕg�̊������Ȃǂ�萫�I�E��ʓI�ɂ������������ɂ�������炸�C�g�̐������̎�������Ȃ��D��w�Ŕg��������ہC�V�������g�̎����������Ƃ��Ȃ����Ƃɔz�����Ȃ��Ƌ�����ʂ�������Ȃ����낤�D
�V�����w�K�w���v�̂̕����̍��ځi�\3�j���݂�ƁC�u����I�v�C�u����II�v��ʂ��āC�d����H�ƔM�͊w���ɒ[�Ɍy������Ă���i���ۂ͋��ȏ����M�҂����ڂ�₢�Ȃ��玷�M���Ă���̂ŁC���Ƃ��J�o�[����邾�낤���c�j�D����̊w�K�w���v�̂́C�g���I�h��3���폜�Ƃ������Ƃ��������C���Z�����͂قƂ�nj����Ă��Ȃ��D�u����I�v�̋ɒ[�Ȍy�ʉ��̉A�Ɂu����II�v�̒��ߖ������邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��D
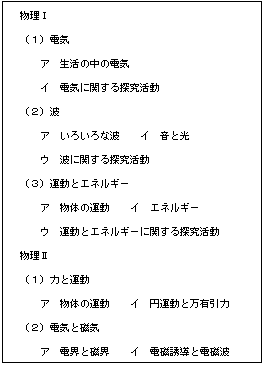
�@�@�@�@�\3�@�V�����w�K�w���v�̂̕����̍���
�u�����T�v�́u�����̒��̓d�C�v�Ɓu���̂̉^���v�͑�ό��肳�ꂽ���̂Ȃ̂ŁC�d�C��^����������ƈ������߂ɂ͢�����U������炽�߂Ċw�Ȃ���Ȃ�Ȃ��D�܂��C�u�����U�v���i�R�j���i�S�j�͑I���ł��邪�C�����I�ɂ͍��ڂ��������D�w�Z�T5�����Ŗ{���ɗ��C�\���H�Ƃ�����肪�c��D����18�N�x����́C���̂悤�Ȉ������Ŋw�w������w�ɓ��w���Ă���̂ŁC��w�ł͂���܂��������̍u�`���s��Ȃ��ƁC�܂��܂��g���������h�������Ă��܂��\��������D���̂��Ƃ���ɋ����������D
�@�Z���^�[�����Łu�����v�Ɓu�����v���������Ԙg�ōs���Ă���[�Ғ��F����16�N�x�Z���^�[�����ł́C���ȇ@�i�u�������ȁv�C�u�����h�`�v�C�u�����h�a�v�j�C���ȇA�i�u���w�h�`�v�C�u���w�h�a�v�C�u�n�w�h�`�v�C�u�n�w�h�a�v�j�C���ȇB�i�u�����h�`�v�C�u�����h�a�v�j�ƕύX�ɂȂ���]���߁C���Z�ł́u�����v�Ɓu�����v�����𗚏C���邱�Ƃ��ɂ߂Ă܂�ɂȂ��Ă��܂��Ă���i���Z����ł̎w����C��ނ����Ȃ��Ƃ��낪����j�D���Z�̎��Ԋ��ɂ��ē���ɓ��w�������n�w���Ώ�(�T���v����147�Z)�ɂ��Ē����������Ƃ���C�g�u�����U�v�܂łƁu�����U�v�܂ŗ����C�����I�ɂ͗��C�\�h��19�Z���������C���ۂ͂قƂ�Ǘ��C����Ă��Ȃ��D�g�u����IB�v�Ɓu����IB�v�����C���C�\�h��20�Z����C�������C���Ă��鍂�Z��4�Z�������D���Z�̐搶���̒���(�T���v����30�Z)�ł������悤�ȌX���������D����ŁC������w�����̒�����эZ�̒��ɂ́g��`�Ƃ��āu�����U�v�܂łƁu�����U�v�܂ŗ������C�����Ă���h(1�Z)���������D2002�N3��28���t�����18�N�x����̃Z���^�[�����̏o�苳�ȁE�Ȗړ��ɂ��ā\���Ԃ܂Ƃ߁\��F
�o��Ȗڂ͢���Ȋ�b��C����ȑ���A��C����ȑ���B��C������T��C����w�T��C������T��y�Ѣ�n�w�T���7�ȖڂƂ��C���̂悤��3�O���[�v�ɕ����C���ꂼ��̃O���[�v�ɂ����āC1�Ȗڂ�I��������D
�O���[�v�i�P�j�F����Ȋ�b��C����ȑ���A��C����ȑ���B��C������T��C
�O���[�v�i�Q�j�F����w�T��C
�O���[�v�i�R�j�F������T��C��n�w�T�
�ɑ��C���̂悤�Ȏ��Ԋ������\����邱�ƂŁC���Z�̎��Ԋ����K�肳��邱�ƁC���Z���̉ȖڑI���̓����ɑ�ψ����e����^���邱�Ƃ��C������w��̈ӌ����(2002�N6��19��)�ői�����F
�@�d�v�ƍl���錴��
�@�P�D��w�����Z���^�[���������Z�̃J���L�������⍂�Z���̗��C�I���̌X���ɑ��āC�s�K�v�Ȑ����U���������Ȃ��悤�ő���̔z�������邱�ƁD
�@�Q�D�I���Ȗڂ̕��������ł������m�ۂ��邱�ƁD
���̒��ő�Ă�2�Ē������C���̌�C�����c�_���������Ă���悤��[�Ғ��F����18�N�x����̃Z���^�[�����ɂ��Ă̍ŏI�܂Ƃ߂�
http://www.dnc.ac.
jp/center_exam/18kyouka-saishuu.html
]�D
�@��w�����Z���^�[�����ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă����F
����w�̗��n�w���̎u�]�҂�����1�Ȗڈȏ�� �� �䂪���̗��n�̋��ʒm���̃��x�����K��i�Z���^�[���������݂���ȏ�C�䂪���̃T�C�G���X���e���V�[�i���n�w���ɂƂ��Ă��j�́C�Z���^�[�����͈͂ł���j.
���O�̊w�K�w���v��(����ȇT��{������)�̎���܂ł́C�������͈͍̔͂��Z�����̂��ׂĂ͈̔͂��Ӗ������D���������݂́C�����IA����邢�͢����IB��̂݁D����18�N�x��������͢�����T��̂�(�V�w�K�w���v�̢̂�����T��͂��̂��Ƃɔz�����Ă����Ă��Ȃ�)�D
���e���Z�̃J���L�������������ȖڎΉ��ɂȂ��Ă����ɁC����ȑ���A��C����ȑ���B����邢�͢���Ȋ�b����I��K�C�̏�Ԃł́C�v���Ȗڑ���͖���(�������i�҂��������邾��)�D
���܂��w�K�w���v�̂̉Ȗڍ\�������߂邱�Ƃ��挈�D
���勦���g�Ȗڂ����点�h�Ƃ����āC���ɍ��Z����ł́g�����ȖڃV�t�g�h���o���オ���Ă���Ƃ���ɁC���x�́C���̍��勦���g�Ȗڂ𑝂₹�h�Ƃ����Ă���D��ςȂ͍̂��Z����ł���C���Z�����g�ł���D������������̌���������Ƃ悭���āC���낢��Ȃ��Ƃ����߂Ă����ׂ��ł���D
�@�k�喼�_�����̖k���������̎w�E�ɂ�莄���C�Â������Ƃ����C���{�̊w�K�w���v�̂́g�\����`constructivism�h�̗���̉e���𑊓������Ă���悤���D���͕č��������ŁC�č��ɗ��w��������w�҂���Ɋw�K�w���v�̘̂g�g�݂������Ă���D���̎咣�́C�ꌩ�����Ƃ��炵����������̂����C���̔��Ȋw�I�Ȑ��i�͐[���Ȉ��e��������ڂ��D���Ƃ��C�u���w�Z�w�K�w���v�̉�����ȕҁv(����11�N5��������)�́u��2��
��1�� ���Ȃ̖ڕW�v�ɂ́C�g���R�̓����͐l�Ԃ̑n���̎Y���ł���Ƃ����l�����ł����h�C�g���݂̉Ȋw�̗��_��@���ɂ��Ă̍l���������̂悤�ɕω����Ă��Ă���Ƃ����Ă���D����́C�Ȋw�̗��_��@���͉Ȋw�҂Ƃ����l�ԂƖ��W�ɐ�������C��ΓI�E���ՓI�Ȃ��̂ł���Ƃ����l��������C�Ȋw�̗��_��@���͉Ȋw�҂Ƃ����l�Ԃ��n���������̂ł���Ƃ����l�����ɓ]�����Ă��Ă���Ƃ������Ƃł���D���̍l�����ɂ��C�Ȋw�͂��̎���ɐ������Ȋw�҂Ƃ����l�Ԃ����F�����L�������̂ł���Ƃ������ƂɂȂ�D�Ȋw�҂Ƃ����l�Ԃ����F�����L�����{�I�ȏ������C���ؐ���Č����C�q�ϐ��Ȃǂł���D�i���F�A���_�[���C���͍u���҂ɂ��j�h�Ƃ��������肪����D�����ł́C���R�̖@�����l�ނƖ��W�ɂȂ藧���Ă�����̂ł���C���Ƃ��l�ނ��łтĂ����R�͍��Ɠ����悤�Ȗ@���ɏ]���Â��邱�Ƃ��Y����Ă���D���̍l����������̌���Ɏ������܂��ƁC�g�^����m���͊e�����\��������̂ł���.
�����ǂ��l���������厖�ł����āC���ꂪ���ՓI�Ȃ��̂ł��邩�ǂ����͑厖�ł͂Ȃ��h�Ƃ������ƂɂȂ�C���̂悤�Ȕ��Ȋw�I�ȍl�����̂��ƂɁC���݂̗��Ȃ���I�w�K�̊w�K���s���Ă���̂ł���.�\����`�̍l�����ɂ��C�w�p�_�����g�_���Ƃ��Ă̑̍فh��������Ƃ��Ă���Γ��e�͂ǂ��ł������Ƃ������ƂɂȂ�D���̍l�����̔��Ȋw���ɂ��ẮC�A�����E�\�[�J���炪�\����`�̐l�����̊w��Ɂg�\����`���h�ȃX�^�C���̋U�_���𓊍e���C�f�ڌ�ɁC���ꂪ�������U����w���Ȃ��N�ł������Ɏw�E�ł���悤�Ȑ��w�E�����w��̂ł���߂ƒZ���I��ʉ��Ƃ��Ȃ����킹���ł����グ���_���ł��������Ƃ����\����`�ŁC�s���ᔻ����(�����F�u��m��̋\�ԁ\�|�X�g�E���_���v�z�ɂ�����Ȋw�̗��p�v�A�����E�\�[�J���C�W�����E�t���N����(��)�C�c�萰����(��))�D�č��̃i�V���i���X�^���_�[�h���\����`�̍l�����ł����Ă���C������܂Ƃ��ɍ̗p�����J���t�H���j�A�B�̐��w�̐��т��C�S�B�őS�čʼn��ʋ߂��ɂȂ����D���{�̊w�K�w���v�̂��C�g�q�ǂ������������ʼn�����������悢�̂��h�Ƃ����l�����ɂȂ��Ă��܂����D�k�������w�E���Ă��邪�C���w�Z���Ȃ̊w�K�w���v�́E����̒��ɁC��Ȋw�I��Ƃ������t���C��������飂Ƃ������t�����ꂼ��1�ӏ������o�Ă��Ȃ��DWeb��ɖk�����̎咣���C�\����`���x�����Ă���l�̎咣���ڂ����Ă���̂ŁC�����F������������Ă������������D
���^����
���F���ȐU���@���ł���50�N�̊Ԃɑ��z�̗\�Z���g���čw���������ނ��ǂ̍��Z�ɂ�����Ǝv�����C���̍��Y���ǂ̂悤�Ɋ������Ă����ׂ����D
�������F���l�̗p�ӂ����������u���g�����Ƃ���ƁC�������Ď�Ԃ⎞�Ԃ�������g���Â炢���́D���炽�߂ė��ȐU���@�ŁC�����ŕK�v�Ƃ��錻��I�ȑ��u�����R�ɍw�����āC������g���ق��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���D
(8) �������_
�����̃p�l���[�Ɖ��Q���҂Ƃ̊Ԃő��l�Ȋϓ_������݂̂Ȃ��ӌ��������s��ꂽ�F
���F�Ȋw�Z�p���̂��̂����̑��ʂ������Ƃ��痝�ȗ��ꂪ�N�����Ă���Ǝv���Ă��邪�C�ǂ����l�����D
�������F�m���ɉȊw�Z�p�͕��̑��ʂ������Ă��邪�C�Ȋw�Z�p�����ň������Ƃ��N�����Ă���킯�ł͂Ȃ����Ƃ������D��������̑��ʂ���v���ł��邱�Ƃ͂�����ŁC�����̐����I�ȕ��ɂ���ċ����قǑ����̂��Ƃ��킩��C�Ƃ������Ƃ�`���邱�Ƃ��D�w��������낱�тƁC��������ƂɐV�������ɗ����������͂⎩�M�����̂��C�ł��{�l�̂��߂ɂȂ�D
��n���F�ُؖ@�I�Ȑ��m�̃T�C�G���X�͍s���~�܂肾�Ƃ����l������D�����ƌ��ʂ��P�P�ɑΉ����Ă���ƍl���邪�C�����ȒP�ł͂Ȃ��D�������q�̏\�������@�̍ŏ��ɢ�a���Ȃ��ċM���ƂȂ��C�w�����Ɩ������@�Ƃ��棂Ƃ��邪�C��a��́u�����Z�v�̂��Ƃł͂Ȃ����D��S��������C��g�[�^���łǂ��Ȃ̂���Ƃ������z���炤�܂�Ă���̂����{�̢�T�C�G���X��ł��낤�D
�쏟���F���Z�ȉ��̊w�K���e�ɐ������������Ă��邪�C��n���͂ǂ����l�����D
��n���F������Ƃ������Ƃ͐搶���炪�͂��������ƁD�����ŏ��߂Đ搶�ɕt���čs�������Ǝv���C���̐搶�̌������Ƃ��ꐶ�����w�ԁD�搶�����m�����̂Ƃ����čs�����Ƃ��厖�D���܂ɐ搶�����������Ă��C���̐^���Ȏp�����āC��������܂��w�Ԃ��̂��D
�쏟���F������F�����₷������̂��w��̎d���ŁC�ǂ̂悤�ɓW�]�������Ďx�����Ă����������D
���F���C���̒���ǂ����Ă������Ƃ��������𐢂̒��͎x���������C�Ȋw�Z�p�����̑��ʂ������n�߂��Ƃ��C�Ȋw�҂͂��ꂩ�瓦�����D���{�ōł����ȗ��ꂵ�Ă���͉̂Ȋw�҂ł��莩���̐�債���S�������D�Љ�Ɏx������镨���Ƃ͉����������Ɛ^���ɍl����ׂ��D����ɂ́C�܂������w�҂��T�C�G���X���痣��Ȃ����Ƃ��D
��n���F�u���Ƃ͉����v�ƍl����ƕ��������w���������܂܂��D���f���ꂽ�Ȋw����͉��������Ă��Ȃ��D
�쏟���F�Ȋw�Z�p����́C����4�E5�N�̊ԂɊ�@�I������̂ł́D���炩�̑[�u���u����ׂ��ł͂Ȃ����D
�㓡��F20���I�ɔ��W�����Ȋw�Z�p�ɕ��̑��ʂ��o�Ă����̂��C�Љ�S�̂��ے�I�Ɍ���悤�ɂȂ��Ă��܂��C�Ȋw�҂�Z�p�҂͂�⎩�M�������Ă����悤�ȕ���������D�w�Z����ł��C���E���w�Z�ł͋��炷��͂���܂��Ă��Ă���Ƃ��������D���낢��Ȃ��Ƃ������I�ɍ��킳���č��̊�@�I���N�����Ă���ƍl������D�w��ōs���Ă��Ă��銈���͊w�Z�ȊO�ōs���鋳��ł���C���コ��ɐϋɓI�Ɏ�g�݂����D
�������F���オ�ς��Љ�v��������͈̂���Ă��C���ꂼ��̎���ɓ������Ƃ������Ȃ���i��ł��Ă���D�w��Ƃ��Ďx���ł�����̂ɂ͎x�����C3�w��ŋ��͂��ăt�B�[���h�����Ă����K�v������D
�������F��͂蕨�����w��Ƃ��Ă������苳���Ȃ���Ȃ�Ȃ��D���̈���ŁC�Љ��S�̐����K�v�D�l�ނ��ʂɊw��W�����Ă����̂́C���̕��@���l�Ԃ̔]�̗e�ʂ̌��E�܂Ŏg���Đ�含�����߂�̂ɓK���Ă�������ŁC���̐�含���g���đ����I�Ȍ������ł���D�w�Z�Ő�含��������S���Ȃ���C�����I�Ȍ������ł���悤�ɋ��炵�Ă������Ƃ��ł���D�l���邽�߂̒m���Ɠ�����C���̗L�����������Ȃ��狳�������Ă��������ɁC���邫���������炠�邱�Ƃɢ�͂܂风����K������D���̂Ƃ��Ɏ~�߂����Ȃ����Ƃ��厖�D�ꌩ�g���h����X�s���A�E�g�����C���܂܂Œ~�ς����w����g���Ă�������Ȃ炢���̂ł͂Ȃ����D�K�v�Ȃ�܂��߂��Ă���D�܂��C�n�����͎��s����̐ςݏd�˂��琶�܂�Ă���Ǝv���D�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����D
���c��F����Ƃ͐l����邱�Ƃł���D����͐l�Ɛl�̊W�C�܂苳����҂Ƌ�������҂Ƃ̊W�������ւ�厖�ŁC���������邩�C�ǂ������邩�Ƃ������Ƃ����厖�D�Ȋw����E���ȋ���ł́C���R�̐ۗ����Ȃ킿���ʗ����͂����藝�������邱�Ƃ��厖�ł���D
����F���E�I�ɕ�������ւ̐i�w�҂���������X��������C��@�I�l���������Ă���D���{�Ɠ��̖������邩������Ȃ����C���B�ł�����������C���ʂ̖�肪���݂��Ă���\��������D2002�N12����2003�N3���ɁC�p���C�h�C�c�C���`�ɓn��e���̐��x�������ہC��w���x���̕�������ɂ��Ė��Ɍ�������@��������D�ނ�����{�Ƌ��ʂ̖�������Ă���Ƃ����F���Ɠ����ɁC���{�̑�w���炪���܂�ɂ����ɕ��Ă��邱�Ƃɔ��Ȋ�@�����������D�p���ł́C50�N���O����C���������̖��𑼂̑�w�̕����̋����ɗ\�߂��̑Ó������`�F�b�N���Ă��炢�C������C�̓_���ʂ̑Ó������O���̋����Ɍ��Ă��炤�Ƃ������x������D�w����4�N�Ԃ����đ����̋����̋������đ��Ƃ��Ă������C���̃g�[�^���ł̉e������D������{�ɂ����Ă��C���S�̂��狳�������V�X�e�}�e�B�b�N�ȃA�v���[�`���l�����Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���D
�R�D������
�@����ꂩ��C3�w��ō�����p�����ċ������V���|�W�E�����s���C���ʂ��镨������E�Ȋw�Z�p����̏����ɑΏ����Ă������Ƃ����ӌ����o����C�����ŁC����ɑ��闝���������ꂽ�D
�Ȃ��C����̂R�w������V���|�W�E���J�Âɂ�����C�����̌��n���s�ψ�����͂��߂Ƃ���W�����ɁC�����i�K���瑽��Ȃ����͂Ƃ��s�͂����D���炽�߂Ē��S��芴�Ӑ\���グ�܂��D�܂��C�{�w��̌��e�쐬�ɂ�����C�u���҂Ȃ�тɔ����Ҋe�ʂɌ��e�����ǂ��Ă����������D�W�e�ʂɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��D
���{�����w��u��w�̕�������v�� (2003-2��) pp.81-88.